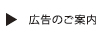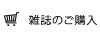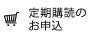公開日 2025年04月04日
ヒマラヤのクンブー谷にあるアマダブラム山(標高6856m)は、険峻な主峰に抱かれるように穏やかな前衛峰が位置し、まるで母が子を抱いているように見える。アマ・ダブラムとはシェルパ語で「母の首飾り」という意味があり、ヒマラヤ山脈で最も美しい山のひとつとされる。
8日目
環境に同化する難しさ
昨日は体調が良かったので、元々今日は休養日だったのを飛ばして、往復7時間ほどかかるC1(キャンプ1・標高5795m)まで行き高度順化したい、とガイドのフルパさんとゲルさんに申し出たが、あえなく却下された。
「もう少し休んで、現在の標高(4550m)に完全に慣れてから次に進んで下さい」と。
恐れていた高山病の症状が、真夜中に出始めた。息苦しさで目が覚める。肺いっぱいに深呼吸するが、酸素をうまく取り込めない。昨日の昼間はなんともなかったのに。そうだ、今まで3回、毎回4000mを超えた所で、なおかつ深夜に発症してきたのだ。エベレスト街道のペリチェで、アンナプルナ内院で、キリマンジャロで。人間の能力なんて、変わるはずがない。高所順応の練習なんて日本ではできない。
頭痛もひどい。吐き気がする。仕方ない。高山病の初期症状に効くとされるダイアモックスを飲もう。高山病特有の強烈な頭痛を抑えるという頭痛薬フィリマイドもだ。
深夜にも関わらず、建物に叩きつける霰と横殴りの風の音がする。「深夜にも関わらず」というのは、ここの所、深夜の天候は安定していたからだ。頂上への最終アタックは夜8時にC2のテントを出て、明朝の午前6時頃までに標高差1090mを一気に攻め落とす計画だ。行動は夜を徹したものとなる。夜間の天候が荒れることは、良い傾向ではない。
昨日、登頂に向かったロシアチームが、C1で撤退してベースキャンプに帰ってきた。ロッジ裏のヘリポートにヘリコプターを呼び、カトマンズまで一気に帰れるようヘリ会社と衛星電話で交渉していた。
エベレスト山域からカトマンズまでのヘリチャーター代は40万円ほどらしい。遭難者の救助も、それほど上乗せされた料金ではないという。遭難者を助けるためにヘリが墜落し、レスキュースタッフが亡くなった話はいくつも耳にする。2023年に入ってから、ヒマラヤ全域で3機が墜落したそうだ、たったの5カ月で。幸い死亡者は出ていない。命のリスクの高さの割には、料金が安すぎる気がする。
明日からC1に向かうという韓国のクライマーは、たくさんのキムチを持ち込んでいた。
□
今日、ポーターのマイラさんと、クライミングガイドのゲルさん2人は、頂上アタックに必要な物資の荷揚げをC1まで行う。酸素ボンベ2本、テント、岩場のクライミングに必要な装備、最低限必要な6食分の食料+予備2食などだ。
先だって日本を訪れたガイドのフルパさんが、大量の日本食を仕入れてくれていた。気の回し方が尋常ではない。フルパさんは今日からエベレスト登頂をしている仲間と顧客のサポートのためエベレスト方面へと向かう。7日間ありがとう。僕がアマダブラムに登るために必要なノウハウを徹底して授けてくれた。「バンドーさんが登頂したら、また下で逢えますよ」。ここまで、これからも助けてくれる3人のため、絶対に頂上に立ちたい。
□これからの予定
5月16日(火) ベースキャンプ(4550m)で休養
5月17日(水) C1(5795m)に高度順化、BCに戻る。
5月18日(木) プジャという安全祈願の祈祷をお坊さんに行ってもらう。その後は休養。
5月19日(金) 登攀開始。BCからC1へ。テント泊。
5月20日(土) C1からC2(5980m)へ。テント泊。
5月21日(日) C2から夜8時に頂上(6885m)アタックへ出発。午前6時頃に登頂後、C2に下る。テント泊。
5月22日(月) C2からBCに下る。
□6000mからの高度順化に失敗した場合
5月21日(日) C2からいったんベースキャンプに戻る。
5月22日(月) 休養。
5月23日(火) 再挑戦。ベースキャンプからC1へ。
5月24日(水) C1からC2へ。
5月25日(木) C2から頂上アタック、C2に下る。
5月26日(金) C2からベースキャンプに下る。
当初はベースキャンプ入りが5月21日、登頂が5月30日の日程だったので、10日間手前に組み直した。スピード勝負に入っている。
夜中にあれほど苦しんだのに、朝にはすべての症状が収まっていた。これが高度順応なのか、単に夜だけ繰り返される現象なのかはわからない。今夜過ごしてみればわかるだろう。
ロシア隊がヘリで去っていった。ガイドとポーター合わせて8人ほどの大きなチームだ。荷物だけみても30㎏程のバッグや樽が10個ほどあり総重量300㎏の大所帯。これだけの準備をしても、C1(5795m)までしか行けず撤退なのか。
ここまで僕を引っ張ってくれたガイドのフルパさんが離脱し、エベレストBCに向かう。昨晩の荒れた天候で、エベレスト上部の登山隊と無線連絡がつかなくなっているそうだ。登頂に成功しようとしまいと、食糧や酸素ボンベを使い切る今日には、登山隊はベースキャンプに下っていなければならない、という。若い日本人のクライマーも1人加わっている。いつも陽気なフルパさんが心配そうな表情をしているのが気がかりだ。
ポーターのマイラさん、クライミングガイドのゲルさんがC1にデポする荷物を持ってベースキャンプを離れる。夕方4時にはここに戻る予定。ロシア隊とは規模がまったく違うわれわれは、荷物重量40㎏程度の速攻隊だ。頂上アタックもゲルさんと僕の2人だけで、C3をすっ飛ばしていく。
韓国隊の2人は今日から登頂に出かける。英語が通じないが、交わす笑顔でお互いに気持ちは通じ合っている。「元気で」「安全を」「幸運を」と声をかけあう。2人は手を挙げながら山へ去っていった。
40室はあろうかという広いロッジに残ったのは僕一人だ。昼まで休息をとり、酸素順応のため近くの小山を登ってみたかったが、ロッジごと濃い霧に包まれており断念する。今日は荷物の整備でもしていよう。
昼過ぎに一人のクライマーが登ってきた。ニュージーランド人のライナーさんは、ヒマラヤ登山経験豊富だが、3週間程前にアマダブラムに登ろうとして悪天候に見舞われ、C2に3日間閉じ込められた挙句、登頂を断念した。他の山をいくつか登頂してのアマダブラム再チャレンジに訪れた。ネパールにはもう3カ月いるという。
しかし、会う人すべて撤退の話ばかりだ。大規模隊と個人の優れたクライマーも断念している。今更ながらアマダブラムの困難さを再認識する。
山岳専門の天気予報サイトでは、僕たちが最終アタックを行う土曜の深夜がやや曇り、日曜の朝は晴天と出ている。この10日間でそんな好コンディションは、その時間帯にしかない。恵まれている、ということか。
9日目
薄い空気の中で
朝6時過ぎにベースキャンプを出てC1への往復に出かけた。5000mオーバーは今回の旅では初めてであり、医学的に重篤な身体損傷が現れるという5500mからの身体の変化を確かめたかった。もちろん頂上アタック時のルートを確かめる事も大きな目的だ。
ベースキャンプ泊の初日は呼吸不全と頭痛が出たが、2日目の昨晩はまったくの正常で熟睡ができた。とりあえず4500mレベルはクリアしたということか。
ベースキャンプを出てものの1時間で5000mに達したが、特に身体異常はなく快調だ。ここ数日の雪模様で5000mから上は、広いモレーン状の谷が雪で覆われている。気温がマイナス10度を下回っているためか、雪は氷のように硬く締まっていて、歩くには大して苦労しない。
ベースキャンプのロッジで飼っている2匹の犬が標高5100mくらいまでついてきた。足元にじゃれついたり、2匹でたわむれたり、雪をガジガジ食べたりと元気そのものだ。
5300mあたりからロッククライミングになる。簡単なフェーズなので、アンザイレン(滑落防止のために2人がロープで身体を結ぶ)は必要ないが、なんせ高所ゆえの呼吸の苦しさゆえに、ちょっとした岩を越えるにも息が荒々しくなる。昨日登頂にでかけた韓国隊が山を下ってきた。昨日、C1に達するまで13時間も掛かったそうで、登頂を断念したそうだ。山の経験が豊富そうな、柔和な表情の方だが残念だ。
5600mあたりから、手がかりのない逆層の一枚岩が増えて苦戦するが、フィクスロープ(シーズン初めにシェルパが固定ロープを張ってくれている)があるので、滑落の不安はない。
ベースキャンプから5時間58分かけてキャンプ1に到達する。標高差は1300m。
アマダブラムの岩峰の直下にテントが3基、張られている。そのうちの1基は、昨日クライミングガイドのゲルさんが張っておいてくれたものだ。早朝、ベースキャンプの料理人のディボクタマンさんが手渡してくれたお弁当をテントの中で食べる。心遣いが嬉しい。
僕がのうのうと昼メシを食らっている間、ゲルさんは忙しく動き回っている。他の登山隊が捨てたゴミを拾い集め、テント内に放置された生ゴミや穀物を見つけては、岩の上に載せる。気温がずっと零下だから腐らないんだろう。置いたとたん、たちまち4羽の鳥が現れ、人間の残渣をむさぼり食い始めた。
下りは3時間18分でベースキャンプに戻る。ゲルさんに着いていくべく早歩きで下るが、まったく追いつかない。ゲルさんは散歩のような雰囲気でのんびり歩いているようにしか見えないのに。走れる道は全部走ったが、まったく追いつかなかった。
高山病の気配は無いが、さすがに5700m以上は別次元だった。大きく息を吸っても、心臓や脳まで酸素が回らない感じ。岩場では手脚にすごく力が必要なので、末端まで血流が届かず、力が抜け気味なのがやや心配。6000mを越えると、更に世界が違う。さて、どうなることか。
10日目
天と山と地への祈り
昼11時、アマダブラムの麓の村・パンボチェの寺からお坊さんにはるばる600m登ってきて頂き、登山の安全と成功を祈ってもらう。世界最強のクライマー集団であり、ヒマラヤの麓に生きるシェルパ族が関わる登山では、この儀式が行われる。
僧侶が経典を読みあげると、鐘や銅鑼が伴奏のリズムを刻む。器に満たされた酒やウイスキーに僧侶は時おり米粒を撒く。 小さな炉にシダの形をした香草がくべられる。白い煙がもうもうと立ち昇る。
朝からずっと分厚いガスがかかっていたアマダブラムの頂上が、雲の切れ間からその姿を見せた。こういう偶然はあるのだろうか。神がかりすぎて、うまい言葉が出てこない。
始まって1時間ほど経つと、僧侶の手元に丸めてあったタルチョ(経文を書いた何枚もの布)に、孔雀の羽に浸した水をふりかける。そのタルチョを鋭塔とロッジの屋根に渡し、結びつける。
祭壇に備えられた揚げドーナツとお菓子とミルクティーが参列者に振る舞われる。
僕とガイドのゲルさん二人が、酒の満たされた器を持って祭壇の前に立ち、それを空中に放り投げる。僕のダウンジャケットは酒でびしょ濡れになる。さらに、小麦粉を僧侶と参列者が手に持ち、3回空中に向けて投げる。あたり一帯、小麦粉だらけだ。
読経は2時間にわたって続いた。式典が終わると皆で食事をするのは、日本の法事に似ている。
(つづく)