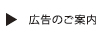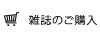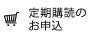公開日 2025年04月11日
ヒマラヤのクンブー谷にあるアマダブラム山(標高6856m)は、険峻な主峰に抱かれるように穏やかな前衛峰が位置し、まるで母が子を抱いているように見える。アマ・ダブラムとはシェルパ語で「母の首飾り」という意味があり、ヒマラヤ山脈で最も美しい山のひとつとされる。
僕は10代の後半から20代の前半にかけて、バックパッカーをやってきた。リュックに生活道具一式を詰め込んで、最小限の金で、あてどなく旅する人のことだ。当時はそういう呼び名はなくて「貧乏旅行者」と呼ばれており、また自分でもそう名乗っていた。
要するに世間からドロップアウトした人間だ。
イランのテヘランではメッカ巡礼者と一緒に1泊5円の地下室に泊まった。デコボコの赤土の上に筵が敷いてあった。 密入国や、赤線巡りや、草を嗜むなど、人に褒められることは何もしていない。社会に貢献する気持ちはさらさらなく、タンポポの綿毛のように風の吹くままに生きていた。
まともに生きようと考えたのは、アフリカのジャングルに生きる人たちと出会ってからだ。彼らのほとんどは、生まれた村から生涯一歩も外に出ない。村の外に世界が広がっていることにも無頓着だ。ところが、生まれて初めて目にした外国人の僕に対して、徹底的に優しく、おおらかな態度で接してくれた。一夜の屋根と壁を与え、食事を分け与えてくれた。
なにかを知るために、遠くに行く必要なんてないのではないか?と思わせられた。
僕がその国を離れてから数年後に、大量虐殺が起こった。百万人とも言われる人が死んだ。僕が旅し、最も世話になった人たちが暮らす村や街の名前が海外通信で伝えられた。僕に力があればジャーナリストになって、日本ではまったく現地報道されないその地域に向かっただろう。
しかし、僕にはその能力も勇気もなかった。そこに戻ることが怖かったのだ。ナタで首を刈られる恐怖からは逃げられなかった。人間失格である。
僕はその事で大きな敗北感に打ちのめされた。一番やらなければならない事から逃げ出した事実から、目を背けられない。
尊敬するアフリカの人たちに習って、生まれた街で生きていくことに決めた。会社をはじめたら、冒険やエクストリームをやる余地などまったくなくなった。とにかく月末と給料日に支払うお金をどうにかする、それしか頭にない。
そこそこ会社が安定してからは、ウルトラマラソンを始めた。250㎞とか520㎞とか、長い距離を走るのが楽しかった。本来やりたいことが時間的にできないから、週末のひとときを利用した「旅」や「挑戦」の代償行為として走っていたと思う。そこにすべてを捧げている人にとっては、いい加減なスタンスのランナーにしか見えなかっただろう。
□
2年前に自由な身になった。時間は無限にある。家の大掃除をしていたら、段ボール箱の中から、高校生の時の生徒手帳が出てきた。カレンダーには今日話しした女子の情報がこまめにメモされており、取材力はなかなかのものであった。そんな事はさておき、手帳の前にも後ろにも、高校を卒業したらやりたい事が雑な字で殴り書きされていた。
ぽかーん、とした。
やるべきことは、高校生の僕がすでに見つけていたんだ。打算なく、外聞もない。単純にやりたい気持ちが叩きつけられている。それなら、残りの生涯をかけてコレをやるしかない。
アマダブラムはその一歩目だ。自分の実力で登れそうな山は選ばなかった。あえて登れなさそうな山を選んだ。うまくいくか、そうでないかは重要だけど、すべてじゃない。やるべきことは決まっている。高校生の時に決めた事をやるだけだ。
11日目
絶不調
さて今一度、アマダブラムという山について。
標高は6858mと、名だたるヒマラヤジャイアントの中では高くない。しかし一般的なノーマルルートでもテクニカルな岩場が多く、ヒマラヤの山の難易度を示す「Major Mountain Expedition」ではグレードⅤ(5)に位置づけられ、8000m峰と肩を並べる。ガイドのジョンパさんによると「エベレストに7回登った人が、この間アマダブラムを撤退したよ」と難しさを表現する。
不安要素が増えた。昨日、岩場で行ったクライミングのトレーニングで、オーバーハング状の一枚岩を、ザイル(ロープ)に装着した1本のユマール(登高器)だけで登る事ができなかったのだ。こんなことは昔は朝めし前だったのに、情けないくらいできなかった。要するに片腕懸垂する力が無くなっているのだ。「こんな難しい岩場は出てこないから大丈夫だよ」とクライミングガイドが肩を叩いて慰めてくれるが、僕の登攀能力に疑問符がついたのは明白だった。
□
朝7時30分にアマダブラム・ベースキャンプ(標高4550m)を出発する。体調がいまいち優れないが、山頂の天気予報がどんどん悪くなっているので、かろうじて晴れ予報の出ている土曜・日曜の山頂アタックに照準を合わせるには今日(金曜)発つしかない。
歩きだすと、おとつい登って高度順応しているはずの道なのに、やたらと息が荒い。ちょうど標高5000mの所にある小山にゼェゼェ息を吸い込みながら登る。おとつい1時間で到達した場所に1時間20分もかかっている。これは変調だ。
標高5100mからの雪原でも調子が出ず、ガイドのゲルさんの目を盗んで、立ちどまって息を整えるが、後方で僕が氷状の雪を踏み抜く足音が消えるためすぐに休憩していることがバレる。5300mからの大岩の折り重なったエリアでは、なおさら遅れが目立ち、待ってもらわないと追いつかない。そして固定ロープの張られた一枚岩の連続ポイントになるとスタミナは続かなくなり、1ピッチ進むたびに岩に手を置いて呼吸が整うまで待ってもらう。これでは、何のためにおとつい順化登山したのかわからない。酷い弱さだ。
標高5795mのキャンプ1に着いたのは15時。ベースキャンプから7時間半もかかった。おとついより1時間半長い。明日の行程は標高差200mではあるが、すべて岩場のクライミングで4~5時間はかかる。体力が必要だ。今夜はたくさん眠って、明日の朝7時30分の出発までに、この原因不明の体調不良を拭い去らなくてはならない。
キャンプ1は、崖の上に奇跡的にある横幅2mほどの棚にテントを張ってある。ゲルさんが、アルファ米をふやかしたのと日本製のふりかけ、味噌汁を作ってくれる。温かくて身体に染みる。
ダウンジャケットを2枚重ねにし、ダウンパンツを履き、マイナス19度対応の高所用の寝袋に潜り込む。高度計がついたガーミンは寒さのためか画面が暗いまま止まっている。肌に密着させていたスマホは電源が入るが、どうせ何も届かないので見る気にはならない。
夕方の4時頃から寝袋に潜り込んだ。5時頃に、テントの外で別の登山者とガイドがキャンプ1に上がってきた気配がした。僕たちより1時間半早くベースキャンプを発った2人のはずだから、ここまで10時間はかかっている。ずいぶん苦戦したようだ。
11日目夜
深夜の苦闘
日が落ちた。眠りにつこうと努力するのだが、息苦しくてなかなか寝つけない。
それが密閉状態に近いテントのせいか、ほぼ6000mという高所の薄い気圧と酸素のせいかはわからない。テントの三方のジッパーを大きめに開けて換気をしてみるが、息苦しさは変わらない。
夜9時30分。呼吸を深くスーハーしても、酸素が身体に回っていないことを実感する。この、半分窒息したような感じで明け方まで8時間を耐えるのは危険な気がした。
何人かのネパール人クライマーにアドバイスされたことを思い出し、試してみようと決意する。「夜、テントで息が苦しくて眠れない時は、酸素ボンベを薄く開いてテントに酸素を充満させたらぐっすり眠れるよ」と。
既に灯りが消えているガイドのゲルさんのテントまで歩いていき「すみません。息が苦しいんですけど、酸素ボンベを1本使えませんか?」と聞く。すぐに灯りがつき「ボンベは使えますけど、頂上アタック用のボンベだから、頂上アタックが難しくなりますよ」と返答がある。
「1本全部じゃなくて、少しだけ使えませんか」と頼むと、ゲルさんは酸素ボンベを持ってきてくれた。
酸素圧力の量をツマミで調整しながら「テント全体に酸素を撒いてしまうより、直接吸った方が効果があります」というので、口にマスクを固定する。
酸素のパワーは絶大で、つけた瞬間から息苦しさがゼロになり、体調不良どころか元気マンマンになる。「酸素すごいですね! しばらくやったら外しますから」とゲルさんに告げる。
しばらくすると、テントの外が騒がしくなる。ガイドの2人が衛星電話であちこちとやり取りをはじめた。ネパール語なので何を言っているかわからない。そしてテントの入口が開くと、2人のガイドが顔を覗かせてこう言う。
「もう一人の登山者の体調がとても悪い。1人にしておけないので、どうするか決めるまで、このテントで彼を寝かせてもらえないか」
もちろん構わない。
登山者がテントに入ってくる。そのままテントの端っこにドッと倒れる。顔を覗き込むと、眉間を歪めて、喋ることもできない。うめき声をあげている。高山病でも酷いレベルだ。その人は、もはや正常な判断ができていなかったと思う。僕が装着していた酸素マスクを見つけると、両手を伸ばしてもぎ取った。そして自分に着けてしまった。
さすがにそれはないだろうと思い、
「あなたは僕の隣に寝てください。二人の顔の間にマスクを置いて酸素をめいっぱい出そう。それでだいぶ楽になるから」と提案しても聞く耳は持たず、マスクは返してくれない。
どうしようもない。
クライミングガイドによると、その登山者は酸素ボンベなしでアマダブラムを登ろうとしたそうだ。要するに登山費用から酸素ボンベ代金を削ったのだと思う。高山病の予防薬や、頭痛薬も持たずにここまで来てしまった。
何カ所かに電話をしていたガイド2人が結論を出したようだ。「今すぐ彼を山から下ろします。そうしないと彼はここで死にます。夜なのでヘリは呼べません」
夜の10時である。岩壁や雪原をヘッドランプだけで乗り越えられるのだろうか。しかも一人は立てるかどうかのフラフラの状態で? 昼間でもベースキャンプまでの下りは速足で3時間の行程だ。多分その倍以上はかかるだろう。徹夜での行軍となる。
しかしガイドの決断は固く「一刻も早く下ろさないと彼は死ぬ」と言うと、彼を担ぎ上げた。
荷物は全てここに残したまま、体重80㎏はあるだろう大柄な登山者を背負って降りるのだという。ガイドの背丈は小柄で、体重は60㎏くらいだろう。シェルパ族という、生涯を山に生きる人たちのすさまじさに圧倒される。これは映画ではなく現実なのだ。
(つづく)