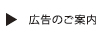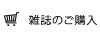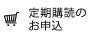公開日 2025年04月18日
ヒマラヤのクンブー谷にあるアマダブラム山(標高6856m)は、険峻な主峰に抱かれるように穏やかな前衛峰が位置し、まるで母が子を抱いているように見える。アマ・ダブラムとはシェルパ語で「母の首飾り」という意味があり、ヒマラヤ山脈で最も美しい山のひとつとされる。
12日目
わざわざ出かける馬鹿の屁理屈
登山者とガイドがキャンプ1を去ると、僕のテントにゲルさんがやってきて「今夜は隣で寝ます。バンドーさんは明日、この先には進めません。朝6時にここを出発し、ベースキャンプまで降ります」と言う。
頭を金槌で叩かれたような宣告だった。確かについさっきまでは息苦しさにもがいていたが、酸素を吸ってからは、元気に溢れ返っているからだ。しかし僕は、「わかりました」と答えた。
アマダブラムに登るにあたって、僕は彼と約束してあった。「最終決断は、100%ゲルさんに委ねる」と。
彼は総合的に判断したのだと思う。
昨日、ユマール(登高器)をロープに噛ませて、片腕の腕力のみで一枚岩を登れなかったこと。
ベースキャンプからキャンプ1までのバテバテの様子。
夜中に酸素ボンベを要求してきたこと。
また、ゲルさん曰く「顔が腫れ上がっています。別人の顔です」。
そして、天気予報の変化。 すべての要素を勘案して「この先には行けません」と判断した。
ゲルさんとしては、ギリギリまで僕を登らせるつもりだったはずだ。明日のスタート時刻を決め、登攀の打ち合わせをしていたのだから。
彼は夜中じゅうずっと、僕の様子をうかがい、凍りついた酸素ボンベの計器メーターの氷を剥がし、数値を確認していた。ほとんど寝ていないだろう。
早朝4時にゲルさんが「酸素ボンベ使い終わってますけど、もう1本使いますか? 山を下る時に吸いますか?」と聞く。もはや元気まんまんで、どちらかと言えば絶好調な精神状態なのだが、下りると約束したので下りる。「酸素はもういらないですよ」と断る。
外は快晴で、太陽を背にアマダブラムの切っ尖が影となって目の前に聳えている。直線距離でも標高差でも1000mを切っている。だけど、僕には遠すぎた1000mだ。
特に最終アタック日の行程は、夜8時にテントを出て、真っ暗闇のなか、10時間かけて岩を攀じ登る予定だった。
その体力は残ってないだろう。そして残す酸素ボンベ1本では5時間しか持たない。無理だ。
目標を失った下山の道は長く感じた。こんなに長くて遠い道を昨日は登って来たのだろうか?と不思議に思った。早く標高を下げた方がダメージが減るので、休憩は1回のみ5分だけにする。カンチェンジュンガはじめ岩峰経験豊富なゲルさんは言う。「アマダブラムはネパールの山でもいちばん難しい山。次回はもっと早めに来て、6000mを何本か登ってから挑戦してください。日本では高い山の練習ができないから、ロッククライミングの練習を頑張ってください」
ダラダラした下りを終えるころに、ヤク(ヒマラヤ牛)の糞の匂いが下界から漂ってきた。とりあえず生きて息をしている。糞の匂いがこれだけ心地よいとは。
□
朝9時40分にベースキャンプに戻る。
すると外庭のベンチで、深夜に高山病のため意識混濁した登山者を背負って山を下りたガイドのジャンパさんが、太陽の方を向いてベンチに深く腰掛けていた。
僕の顔を認めると、立ち上がって握手してくれる。
「朝5時にベースキャンプに着きました。徹夜で7時間もかかりましたよ」。ふーっと深いため息をつきながらニガ笑いしている。
テント下には手がかりのない一枚岩にロープが張られただけ。そして大岩が積み重なるブロック帯を越えると急斜面の雪原だ。そこをどうやって、真夜中に人間を背負って脱出できる?
日本の山とは違って、標識も何もない。かろうじてケルン(石を数個積み上げた道しるべ)がたまにあるくらいだ。日本のケルンのように堂々としたものではない。子供が遊びで3個積んだようなものだ。彼はアマダブラムの専門家ではない。ヒマラヤじゅうの山をガイドしている。真っ暗闇の中、どうやって正しい道を選べたのだ?
「少し寝たからもう大丈夫ですよ」と言うものの、タフネスで精悍な顔つきをしたジャンパさんも、さすがに憔悴しているのがわかる。
□
午前中の晴天が一転、午後から天気は大荒れとなり、ベースキャンプは強い横風と濃い霧にとりまかれ、夜半には大雪となった。この天候の中、6000mに取り残されていたらどうなっていたか。死は、最も大きな可能性の一つだっただろう。
今週、エベレスト山域でも悪天候がつづき、多くの登山者が登頂をあきらめた。そして最悪の事態だが、2人のガイドが亡くなったそうだ。割れ落ちた雪の塊の下敷きになったという(のちに同日前後に18人もの登山者とガイドが遭難死したことを知る)。
ここでは生と死が隣合わせにある。恐ろしいまでの美しさを湛える山は、近づくと暴君に変身する。
そんな所にわざわざ行く必要などないだろう、というのが常識的な考えだ。
しかし、あえてこんな場所に来る人は「つき動かされる何か」によって生きている。わざわざ行かなくていい場所へ行き、わざわざしなくていい事をやる。「そんな馬鹿なことやめとけ」というまっとうで親切なアドバイスをくれる人の声に耳を貸さない。
僕の私観だけど、こう思っている。
人類が誕生したアフリカ東部に止まらず、地球全体に広がったのは、馬鹿がいたからだと。
ムラのコミューンの中にとどまっておれば安全なものを、わざわざ出掛けなくていいムラの外へと、興味津々歩いていった馬鹿。
あるいは、仲間から差別され、村八分にあって追い出された人が、仕方なくムラから逃げ落ちたか。いずれかが人類拡大の先鋒となったと思う。
ムラの中心で長クラスに収まり、良い身分の人は、一生そこに居たと思う。わざわざ危険なムラの外に出て冒険する必要ないから。
□
ベースキャンプの小屋に入って、トイレでウンチをすると、黒檀のように真っ黒な物体が爆発的に発射された。小便は茶褐色の血尿だ。手の甲はグローブみたいに腫れあがっている。想像以上に腕の力を使ったのか上腕は酷い筋肉痛で、肩までしか上がらない。
人間は2日間、異世界にいただけで、こんなにダメージを負うのだろうか。あるいはヒマラヤを攻めるにしては虚弱すぎたか。きっとそうだ。
13日目
猿の反省ポーズ
夜中にトイレに起きると、窓の半分が雪で埋まっていた。ガタガタと窓枠が揺れている。夜半からベースキャンプは横殴りの雪に見舞われている。標高4500mでこれだ。7000m近い山頂はどうなっているか。予定では今夜、ちょうど今頃、頂上アタックの真っ最中だ。もし岩壁に突っ込んでいたら、悲惨な状態になった事は疑いようがない。
下山翌日の今日、キャンプ1までテントや登攀用具などの荷物を回収に出かけたガイドのゲルさんとポーターのマイラさんが夕方に帰ってきた。いつも「大丈夫ですよ」「平気ですよ」しか言わない2人が、「けっこう大変でした」と疲れている。キャンプ1のかなり下で、膝まで雪が深くなっていたそうだ。一晩で山は豹変する。
□
反省する点は多い。
天候を最優先するがあまり、数カ月かけて練り込んだ高度順化の行程を、ネパール入りした日に全てひっくり返してしまった。そのため標高1400mのカトマンズから標高5795mで夜を越すまでに9日間しか取らなかった。今さら思うにナンセンスだ。
僕より遥かに実力が上のクライマーでも、ヒマラヤ入りして3カ月かけて6000m峰を3つこなし、アマダブラムに来ていた。僕がカトマンズから5日目にベースキャンプに来たと言うと、お口あんぐりしていた。そんな彼でもアマダブラムは登れなかった。
とは言うものの、やはり天候は大切で、前述のとおり山を下った日曜の午後から大荒れになった。もし、午前が快晴だからと岩場に突っ込んでいたら命はなかったと思う。下山を促してくれたガイドのゲルさんは生命の恩人である。
更に。基礎体力が落ちすぎていた。指1~2本懸垂や片手懸垂はふつうにこなせなくてはならない。ロッククライミングが経験・体バランス・センスで成り立っているとは言っても、それは基礎体力のベースがあってのものだ。僕はトレーニングといえば走ることだけに比重を置いてきたので、クライマーとしての練習が足りなさすぎた。クライミング…特に腕っぷしが必要なフリークライミングの研鑽を積みたい。体脂肪を落とし、筋力で身体を自在に操れるようにしたい。
14日目
さよならアマダブラム
元々、22日かけて高度に慣れながら登り詰めるはずだったアマダブラムだが、日程を10日間前倒しにしたため、撤退後のスケジュールがガラーンと空いてしまった。
せっかくヒマラヤくんだりまで来ているのだから、他の簡単な山にでも登ればいいものの、標高6000m以上はカトマンズに戻って政府発行の登山許可を得る必要があり、日程的には無理だ。
いったんエベレスト街道のディンボチェ(4400m)まで下り、あまりトレッカーが行かないチョーラ峠(5420m)を越えて氷河を渡り、湖や氷河が美しいというゴーキョ・リ(5357m)に登ってみよう。
首都カトマンズが想像以上に面白かったので、元々は1日だけ滞在して帰路便に乗る予定だったが、3日くらい観光しようか。数百年歴史が止まったような旧市街だけじゃなく、ネパールの高校生たちが行き交うオシャレスポットや、サラリーマンがクダを巻くスナックだってあるはずだ。
□
朝9時、ルクラから今日まで12日間、僕の登攀用具や食料、テントなど20数㎏を背負い続けてくれたポーターのマイラさんが、下界へと帰っていく。
荷上げのために何度、キャンプ1まで登り降りしてくれたことか。数度に分けて上方へと送り続けた荷物を一括りにまとめたため、帰路の荷物は45㎏にもなった。
「長い間、家を留守にしたことを奥さんと娘さんにお詫びしてると伝えてくださいね。何日も僕の荷物を持ってもらったのに、サミットアタックできず、ごめんなさい」と僕から伝えた。
「今回は残念だったけど、あなたは楽しそうだった。またチャレンジしてほしい。来年ネパールに来てください」
と、小柄なマイラさんが抱きしめてくれた。力強いハグだった。小柄な体躯の、どこにそんな力があるんだろう。ネパールの男は本当に強い。
ベースキャンプの正面にある標高差200mほどの丘を登ってみた。小山ながらもピラミッド型をした単独峰で、頂上に立つと360度の展望が開ける。ヒマラヤ襞が刻まれた鋭角の無名峰の連なりや、アマダブラム山塊から生まれ落ちるミンボ氷河に囲まれ、独りで独占するにはもったいない景色だ。
丘をのんびり下っていると、足元には3ミリほどの小さな花弁をつけた高山植物が何種類かあった。今まではまったく目に入っていなかったが、夜間には凍結する寒冷地で、ヤク牛の重いヒヅメに踏んづけながらも、逞しく生きているんだな。
明朝、アマダブラム・ベースキャンプを去る。ベースキャンプに入ってから、都合9日間もいた。たくさんの美味しい料理を作ってくれた奥さんのニマさんと料理担当のディボクタマンさんに感謝します。
ダルバート(ネパールの定食)、チキンカレー、野菜カレー、ミックスピザ、ヤク肉のステーキ(硬!)、ミックスフライドライス、野菜サラダ、フルーツカクテル…ほかいろいろ。そして抜群に美味しいチャ(ミルクティー)。必ずまたここに来ます!
(アマダブラム編おわり)