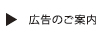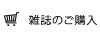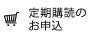公開日 2025年10月31日
本当にやりたいこと社会の内と外
地図のない旅を長くしていた。地図を持たず、太陽の位置や、川の流れの上下や、人からの聞き伝えで、次の目的地を決めていく旅だ。
最初からそうしようとしたわけではない。アフリカのジャングル地帯で完全に地図の空白地帯があり、どうしても東から西へ向かいたかったので、地図のない旅となってしまった。毎日が冒険の連続だった。カバに襲われかけたり、ナタを持ったおじさんに追いかけ回された。その痛快な面白さにトリコになった。
今から向かう先が空白で、まったく何があるのかわからなければ、すべてが予測し得ない出来事となる。木に果実がなってるだけで大興奮し、村や水場が近づいている気配がすると有頂天に達する。
「ロンリープラネット」「シューストリング」「地球の歩き方」といったガイドブックを持って旅をしたこともある。「ミシュラン」の地図に頼ったこともある。ガイドブックや地図にはゆく先に何があるか、すべて書かれている。一ノ瀬泰造が命懸けで目指したアンコールワットも、河口慧海が生涯を懸けた中国奥地も、ガイドブックを読んで予備知識を蓄えて訪れたら、ものすごい遺跡に対面しても特に興奮はしない。「そこにあるのが当然」だからだ。
「地図のない旅」の面白さを、たくさんの方に知ってほしいなって思って、馬鹿道という大会らしきものを始めた。タイムも順位も出さないので、マラソン大会ではないと思う。
道を決めない、地図を使わない、という主旨に対して、ウルトラマラソン界のお偉い方には「ランナーの生命を軽んじている」とお叱りを受けた。
ご参加者には、どんなにコンセプトを説明しても、便利な地図アプリやGPSトラッキングツールを親切にご紹介いただいてしまう。「これがあるとランナーを管理でき、安全ですよ」と。
僕の、面白さを伝える能力が乏しいのか、あるいはそのようなヘンテコな旅の需要がないのか悩みどころである。決まったお休みの日程や、往路・帰路便を予約せざるを得ない若い社会人の皆さんに対して、無理なコンセプトの押しつけをしてるのかもしれない。
ふだん社会の規範や常識のなかできちんと生きてらっしゃる方々を、たまの長い休日に社会の外側、管理の外側へとお招きしたい、と思ってやってるんだけどね~。
やっぱ考え方がインディーズすぎるのだろうか。きっとあたしは推しが5人いるかいないかの地下アイドルなの。
僕たちは自由になるために走ってるんだ
もともと俗世から離脱するために、高校生の頃、走りはじめた。受験戦争や、いずれ加わるのかもしれない社会という規範の外に出るためだ。ゆくあてを決めず勝手気ままに走って、自分の脚ですごく遠くまで行けることが楽しかった。
ゴールなんて決めない。いつ到着するかなんてどうでもいい。ルールから離脱するために、自分の肉体ひとつで旅してるんだ。俺は誰にも縛られないから。
しかし大人になった僕は、ミュージシャンにも詩人にも格闘家にもなれず、あらゆるジャンルで才能のきらめきを見せず、キレるお客さまやキレる部下にぺこぺこ頭を下げるのが得意な社会人になった。
俗世からの逃亡を願う時間的余裕はなく、週末にマラソン大会に出て、タイムや完走を目指す可愛らしい大人になった。
サブ3・5だのサブテンだのをすごく気にしてる一方で、かすかな疑問符がつきまとっている。
十代の僕は、自由になるために、社会から離脱するために走ってたのに、タイムだの、難関レースの完走だの、承認欲求っぽい足かせがまとわりついてる。4 2・195㎞を何時間何分何秒で走ったとか、同じ歳の人のうち全国で何位とか。
多くのランナーが知ってると思うけど、42㎞という距離はギリシャとペルシャの血みどろの戦争に由来している。ランナーって種族の方々は、世界平和を願う穏健な反戦主義な人がマジョリティな気がするのにね。マラトンの丘から、今のアテネ中心部までのたかだか40㎞を走って、兵隊さんが死んじゃった話はめちゃ怪しいね。たぶん後づけのデタラメ。僕はスパルタスロン(246㎞レース・ギリシャ)に出るため10日前入りし、暇をもてあましてマラトンからアテネまで走ったことある。すごく短いです。
中途半端にくっついた195メートルは、第4回の五輪ロンドン大会でイギリス王妃が「宮殿の庭の前でゴールさせなさいよ」とダダをこねて延ばしたということになっている。この話も実に嘘くさい。
そもそも時間やら時刻という単位は、紀元前3500年ごろより古代エジプトだのシュメール人だの古代ギリシャだのの人たちが発明した概念である。
なんでそんな昔のオッサンが決めたルールに縛られなくちゃならないのか。だいたい、ほとんどの現代ルールにギリシャ人が関与しているが、僕は10年以上ギリシャに通いつめて、かの地のおじさんたちが高田純次レベルでテキトーなことを知っている。
もーいいじゃねーか。テキトーな奴らがもともと決めたルールなんだから、そんなにガチで縛られなくていいんだよ。どの道を走ろうと、いつまでにどこに着こうと、他人に決められなくていいじゃないか。
自由になろうぜ。僕たちは、自由になるために走ってるんだ。
旅の途中で。十六歳の地図
那賀町、もみじ川温泉。
夕日がかげるこの場所を、バナナの房をかかえて、僕は西へと走っていた。
遠くへ行きたいだけだった。バーガーショップが1軒しかない街を、飛び出したかった。ハマショーが街を飛び出したい理由を述べた歌詞を聴き間違えていた。「バーが5、6軒の街」の歌詞を「バーガー5、6軒」とさんざん口ずさんでた(2025年の今日に至るまで・・・)。5、6軒もハンバーガー屋さんがある立派な街なら、そこで就職すればいいじゃねえか?と思ってた。
40年以上、走ってる。しかも同じ道ばかりだ。遠くまで行くつもりだったのに、ずっと同じ場所にいる。
速くもなく、強くもなく、いつも足が痛い。何年やってもマメができる。前にぜんぜん進まない。おばちゃんと話ばかりしている。
街にチェーン店のバーガーショップはたくさんできたけど、まだ遠くに行きたい。四国横断の道、290㎞あたりを走ってます。
本当はないもの
だれもが日々、気にして生きている時間や、大切に思ってる誕生日や記念日や、スポーツマンが目標とする高さや距離は、「ほんとうはない」のだ。
長さや時間は、人類史のスケールサイズだとごく最近になって人間が思いついたり、決まり事がまとまったりした。
長さ(メートル)の単位が確定したのは、1983年に真空中の光の速さを基準に。
時間の単位は、11世紀から徐々に工夫がなされたが、基本となる「秒」のセシウム原子時計は1967年に。
暦の基本となるグレゴリオ歴は16世紀に。
メートル法に集約されるまでは、長さの単位はヨーロッパだけで100種類以上あった。
ルールが決まる以前は、それらは「なかった」のである。
さて。自然のなかに放り込まれて、時間や距離の意識をなくすことは、そう難しくない。だって「元々なかった」んだから。
哲学をくっちゃべりたいわけじゃない。気にしなければすごく面白い!って体験をしてほしいだけなんだ。GPSや時計を外すだけでもいい。
誰かにタイム入りの完走証を見せたり、レース報告を数値で知らせない「走るやり方」があるんだ。
自然と、人と、走る自分自身と。世界にあるのが、それだけって考えてみるんだ。基準は自分と周りだけ。計測器には拘束されない。
そんなに難しくないんだ。もっといろんな走り方、オモシロがる方法があるんだ。
野宿と山口百恵
四国を走っていると、道のあちこちに記憶の残渣がこびりついている。
何度も何度も遠くまで走った道。目に映る風景と、そこで遭った出来事。その場所に現れた人と会話。何の目印もない、雑草が生い茂るだけの路側帯なのに、何十年も前の記憶が残っている。
いちばん記憶に焼きついてるのは、野宿した場所だ。どういう気持ちを抱いて(たいていは絶望)、どんな天候の下で(たいていは寒さに凍えてる)、野宿できそうな場所にたどり着き、ひと時のやすらぎを与えられたろう。
野宿は、明治時代より前は、木賃宿に泊まる経済力のない巡礼旅の庶民には、夜を過ごすありふれた方法だった。
イランからパキスタンまで旅をともにした、メッカ巡礼帰りの一家は野宿だったし、アフリカ赤道直下のジャングル地帯で、売り物を背負って運ぶ商人たちも野宿だった。
僕は16歳の時から、徒歩や走り旅のときは、野宿が前提だった。だけど、40歳を過ぎた頃から、野宿に違和感を抱きはじめた。世間に中年男性と評される身なりで、バス停や道端で横になっていたら、目撃した人は何と思うだろうか。おそらく行き倒れか不審者だと案じるはずだ。家の近所にそういう人を発見したら、迷わず110か119に電話するだろう。
健全な旅人として、周囲に違和感をもたらさない野宿年齢は、39歳までが限界なのだ。
しかし僕は、中高年になっても人目を盗んでは野宿していた。昔に比べて、場所選びや時間帯には遥かに慎重になった。田舎街に暮らすお年寄りたちを不安にさせたくないからだ。
そんな野宿人生も、そろそろ終止符を打つべき時が来た。いままで数百泊以上してるが、一度もお巡りさんに職質されたことがないので、僕の野宿道は正しい道を歩んだと誇りをもって言える。
これからは未来ある若い世代に、この素晴らしき野宿文化を伝える役目を担うべきだと決意した。
野宿引退のきっかけは突然やってきた。
先週、四国横断のみちを走っていた。真夜中に、スマホのスピーカーで鳴らしてたYouTube musicが、勝手に山口百恵の「さよならの向こう側」をセレクトしたんだ。そして信じられないほどに、心に痛く染み入った。涙の一粒も流したかも知れない。
今まで何百回と耳にし、何も感じなかった歌に、こんなに心をとらえられるとは。
こういうのは天啓だと思う。バス停のベンチにそっと白いマイクを置いて、ステージを去るときが来たのだ。
人が消滅していく地方に生きること
豊かに生きるとは?という本質的な問いかけ
僕が育った徳島県の南に位置する小さな街は、JR駅があるにも関わらず、商店街の店の大半は錆びたシャッターを下ろしたままで、廃村のような佇まいをしている。街なかに3軒あった食料品店は消え、お年寄りたちは5㎞離れた全国チェーンのスーパーにでかけるのが日課だ。服を買うことも自転車を修理することも町内ではできない。介護施設まで閉鎖した。
地方の街は、おおむねこのような状態にある。
鉄道どころか路線バスまで廃止され、小さなワゴン車を使ったコミュニティバスの運営予算すら確保できない自治体では、乗り合いタクシーしか移動手段がない。こういった町村で産まれた若者は、地元で公務員として職に就く以外は、街を出ていくしかない。収入を得る方法がないからだ。
「あと20年たったら、この街には誰もいなくなる」とお年寄りたちは口ぐせのように言う。
徳島の祖谷地方は「日本三大秘境」と呼ばれ、ランドマークである「祖谷のかずら橋」には主にアジアからのツアー客が大型バスで続々と訪れ、一大観光地として賑わっている。
しかし賑わいは祖谷のかずら橋がある「西祖谷山村」までだ。更に15㎞ほど祖谷川を上流へとさかのぼった「東祖谷」までツアーバスは来ない。
東祖谷は2006年までは「東祖谷山村」というひとつの自治体だった。戦後間もない1955年に8974人が住んでいた旧東祖谷山村は、2025年には951人まで過疎が進んだ。ピーク人口の90%近くが「消滅」したのだ。一方で東祖谷の228平方㎞という面積は、合併した三好市の一地域とは思えない広大さで、リヒテンシュタインなどヨーロッパの小国よりも広い。ほぼ同じ面積の大阪市には272万人が住み、東祖谷には951人だ。
近年、この東祖谷に変化の兆しが見られる。レンタカーや自転車、路線バスなどを使って、単身や2人組の海外ツーリストがひきも切らず詰めかけているのだ。
東祖谷に派手な観光地はない。地元のお母さんが手づくりでこしらえた案山子がたくさん並ぶ「かかしの里」や、「天空の村」と称される落合集落にツーリストは訪れる。が、売店もなければ自販機もない。村全体をみても道の駅や産直市はない。唯一あった温泉施設は閉鎖されたままだ。
ではなぜこの地は、地球の反対側から多くの人を呼び寄せ、魅了しているのか。
コンビニ、ファミレス、ファストフード、ショッピングモール、シネコン、ホール、アリーナ、正確無比な交通網…日本人が、豊かで生活に欠かせないと思っている都市機能とは違う豊かな何かがあるのだ。
この地を訪れる欧米人は気づいている。世界中で日本にしかない、人びとが長い時間をかけて培ってきた豊かな暮らしを、僕たちは忘れているのかもしれない。東祖谷にはそれがある。
走って旅して、わずか2日間だけの体験だけど、何かを見つけてみませんか?
10月10日から12日にかけて「東祖谷おてつ旅」という大会を開きます。天空の林道から祖谷の景色を堪能しつつ、地元東祖谷の皆さんとの交流を愉しむ走り旅の大会です。走り歩く距離は2日間で約90㎞、累積標高2500m。
(つづく)