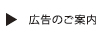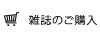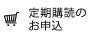公開日 2025年11月14日
足首の骨折から半年、尖ったナイフの先でつんつん突かれるような痛みが取れず。ロッククライミングは無理だと判断し、歩いて登れる標高6476mのメラピーク(ヒマラヤ)へ。リハビリを兼ねた登山のつもりだった。
5日目
ひっそり静まった宿場町で
氷河が削った谷の底の、電気のない宿を出て、いったん4400mまで登り、ひたすら1000m下る。
前方に見えてるのは、マチュピチュを4つ並べたような連山。標高は目算で5800mくらい。さすがにこのカッコよさ、今回こそ山に名前があるだろう。いや、氷の鎧に覆われない山は、やはり冷遇されて無名なんだろうか? こわごわクライミングガイドに尋ねたら、またしても「名前はありません。誰も登りません」とのこと。確かに地図にも名称表記はない。年間何十万人も観光客が訪れるマチュピチュより遥かにスケールが大きく、しかも4個も並んでお得感たっぷり。世界の誰ひとりとして注目していないこの4連星カルテット、腕っぷしのいい日本のクライマーさん、いかがっすか?
さっきまで森林限界の上にいたが、1000m下ると密林と苔の世界に戻った。高峰からの雪解け水が四方八方から集まる渓谷の底は、湿気の巣のようになっていて、永久に乾くことのないぬかるみの世界だ。着地に失敗したら泥地獄に足首まで持っていかれる。
泥には、この道を荷運びの職場とする牛や馬のウンチがたっぷり混じっている。芳しい牛ウンチの匂いは好きだけど、岩にウンチがこびりついた部分はニュルニュル滑って困っちゃう。2回こけた。
標高3580mのコテ村に降りた。けっこう大きな宿場町でホテルが10軒ほど並ぶ。エベレスト街道から離れて、メラ・ピークに向かう人たちとこの村から合流するはずだ。しかし、他の登山者の姿は見えない。今日も、宿に泊まってる外国人は僕ひとりだ。他の宿泊客といえば、ピクニックの中締めか打ち上げかで酒盛りし、アカペラの歌を宿じゅうに轟かせる陽気なネパールの方しかお見かけしない。今、ヒマラヤは雨季あけの商売繁盛シーズンだ。海外登山客はどこに行ったんだろ?
日没前のほんの一瞬だけ辺りを覆っていたガスが晴れ、向かうべき山・メラピークが姿を表した。どの山も美しいけど、特別な魅力を放っている。気負わずのんびりいこう。
6日目
絵画のような谷
風景の様相が一変した。
白い氷雪をまとった峰々が前に、左右に、太陽の光を浴びて屹立している。谷底からの標高差2500mをほぼ垂直に立ち上がり、空間を圧している。現実離れした氷と岩の装飾。しかし対照的に谷底には高山植物の花々が柔らかに咲き、くるくると宙を舞う野鳥たちが美声を競っている。
幾十もの小川のせせらぎを、石づたいに渡る。真昼の月はいつまでも消えず、それが下界である地球の惑星感を昂らせる。
「天国ってこうゆうトコなん?」なんてアホのような感想しか出ない。
まぬけヅラの目を覚ますかのように、爆音が谷に響き渡る。
雪崩だ。
岩々が割れるような、雷音が耳のそばで鳴らされたような、恐怖をともなう音。天下泰平のんびり歩いていたが速足になる。
標高3580mのコテ村からインク川の左岸を上流へ。標高4358mのタクナク村に入り、ここで2泊して高度順化をはかる。
今までの経験では4000m台では高度障害は出ない。軽い頭痛と、登りで心拍数が上がるくらい。しかし5500mを越すと、大きなダメージを負う。僕の場合は真夜中にやってくる。入眠すると呼吸が浅くなり、意識して深呼吸ができない。そのため酸素を取り込めなくなり高山病を発症する。症状は、割れるような頭痛、ひどい嘔吐、顔が腫れあがる満月症などだ。いったん高山病の症状が出ると動けなくなるので、そうならないよう高度順化を慎重にやる。
標高6500mだと気圧や酸素濃度は地上の45%しかない。
8日後に予定している最終アタックの日は、深夜1時から行動するため、今から深夜0時起きの準備をしている。毎日、宿に着くのが昼なので、メシを食べる時間以外はひたすら眠り、深夜0時に起きる。このサイクルに慣れていくのだ。
ヤギの生存競争
標高4358mのタクナク村は8軒ほどのロッジがある宿場村だ。3連山である標高6476mのメラピーク・ノースや、標高8475mのマカルーへと続く街道でもある。この村で、高度順化のために2泊する。
標高差300mの裏山を登り下りする予定だったが、微かに頭痛がするのと、2日前の1000m泥沼下りの筋肉痛があるので、散歩と読書だけにしておく。
明日は標高5000mのコテ村でさらに2泊する。
コテ村を出るとメラ氷河の末端から氷雪上の行程となり、標高5800mのメラピーク・ハイキャンプに入る。頂上への最終拠点だ。
翌深夜にテントを出て、明け方にメラピークの頂上に立つ予定。山頂の天気予報は9月28日まで悪く、降雪量が多く風が強い。29日の夜から好天に転じ、翌日30日も良い。といっても日ごとに予報は変わるので、いつでもアタックできるように準備しておこう。
タクナク村の背後の崖の上に、白い点々があり、ちょっとずつ動いているのでヤギだとわかった。70度ほどの壁である。ヤギさんたちのクライミング能力がうらやましい。そのうちヤギ飼いの声が近づいてきて、窓から見下ろすと宿の周りを何百頭ものヤギが囲んでいた。
ずっと眺めていると、産まれて間もない子ヤギが美味しそうな若草を食べてると、大ヤギが現れ子ヤギを頭突きでぶっ飛ばして、若草を独占する。集団のあちこちで、頭突きの被害にあった子ヤギが仰向けになって足をバタバタしている。のんびり草をはんでるだけの心優しきヤギさんたちかと思えば、子どもだからって容赦しない、厳しい生存競争がありました。
さてこのヤギさん、大人になれば一頭1万円ほどで取引される。急傾斜の山道を何日も歩かされ、やっとどこかに着いたら、人間さまのお肉となるのだ。生きるってことは大変だな。
□
クライミングガイドのゲルさんが、ハイキャンプで食べる用の携行食を見せてくれた。日本食のフリーズドライがずらり。これを2週間も背負い続けてくれてるんだ。これらは同僚が日本に出張した際に、毎回20㎏ほどもまとめ買いしてネパールに持ち帰っているそうだ。
ゲルさんは20代の若さながら、カンツェンジュンガ(8586m)やマナスル(8163m)、エベレスト(8848m)を何度もガイドしている。来年も既にエベレストの予約が入っている。
8000m峰はブランド力があり人気が高く、近年はマナスルやチョーオユー(8188m)の予約が多い。8000m峰の中では高度な登攀能力を問われないからだ。日本人でも70代以上の方々が、男女問わず毎年登頂されている。お仕事を現役引退されてからの目標が、8000m峰を順に登頂していくなんて、ライフワークとして最高なんじゃないかなと思う。
水の中で呼吸するよう
夜になって呼吸が苦しくなる。3回深呼吸しても、1回分にもならない。息をしても息ができないという状態は、非常に精神的に圧迫される。このまま息ができないと、死んでしまうのではないかという単純な恐怖。どういう感じかというと、レジ袋か何かを膨らませて息を吹き込み、何十回か呼吸してみて、中に酸素がなくなり二酸化炭素ばかりなのに、必死に息をしてる状態。息はしても酸素がないから苦しさがどんどん増してくる。
たかだか標高4350mで高山病の症状が出てしまったというショックは大きい。去年のアマダブラムでは6000m付近までピンピンしていたのに。1年でこの差は何なのだろう。
深夜2時にいよいよ呼吸不全が深刻になり、意識を失う前にと、隣の部屋をノックしてガイドのゲルさんに相談する。
「いったん標高を落とした方がいいですか?」と尋ねると、「今すぐ出発しますか?」とのこと。外は漆黒の闇で大雨が降っている。足元は相当危ない。ゲルさんは何度もこういう経験を積んでいるのだろう。僕も真夜中に高山病の登山者を背中におぶって崖を降りていくクライミングガイドを見たことがある。それは避けたい。「夜明けまで我慢します」と答える。
「酸素ボンベを1時間だけ使えませんか?」とも確認した。酸素の威力は絶大で、ものの数分吸っただけでギンギンに回復した経験がある。酸素の容量は6~8時間分はあるはずだ。
しかしゲルさんの答えは厳しい。
「ここで使うと、登頂はあきらめないといけませんが、それでいいですか?」という。
「それはだめです。登りたいです」
夜明けまで待って山を下り、標高を600m下げると決める。
部屋に戻って「賭けだ」とばかりに、高山病の薬ダイアモックスを用法の2倍飲む。あまり褒められた対処ではない。1時間ほど呼吸困難に変化はなく、効いてない気がしてショックに追い討ちをかける。しかしそのうち両手両足がビリビリ痺れ、麻痺してきた。これはダイアモックスの典型的な副作用だ。薬が身体に影響を及ぼしていることで気が休まる。
ハッと気づくと朝4時だった。短時間だが入眠していたのだ。30分ほどだが「眠れた!」という事実に安堵した。昨日から一睡もできていなかった。
7日目
あと戻りはしない
明け方には呼吸困難が収まっていた。ゲルさんの部屋に行き「今日、標高を落とすのはやめて、この村で休みます」と告げる。
標高差600m下の村まで降りて、再びこの村に戻るには、往復20㎞の渡渉やガレた道を越えなくてはならない。体力を消耗するのが嫌だった。また、標高を下げると高度順化を一からやり直すことになり、下の村でいったん収まった高度障害が、標高を上げたこの村で再びぶり返さないという確証がない。何より、今夜が嵐だったように、天候不順が続くなか、週に1度しかない好天の日を逃したくない。
高山病薬・ダイアモックスの影響なのか、利尿が激しく、一晩で2リットルも尿が出ている(テント内で用を足すためボトルに出しているので量がわかる)。
ゲルさんは「とにかくたくさんお湯を飲むこと」「ごはんを食べること」と体力を落とさないようアドバイスをしてくれる。頻繁に様子を伺ってくれる。「何も喉を通らない」と返事したが、器にいっぱいのお湯に浸したごはんと、日本製のダシ醤油を持ってきてくれ「これを全部食べてください」と命令がくだる。口に含むと美味しかった。食べ終わると身体があたたまり、布団にくるまってまた睡眠を取る。起きたら元気を取り戻していた。
(つづく)