文=坂東良晃(タウトク編集人)
若者が嫌いだ!
もう一度叫ぼう。若者が嫌いダーッ!
ソクラテスの時代から、オッサンは今どきの若者が嫌いって決まっているのダーッ!
皆さんは若者が好きだろうか。ぼくは本当に大嫌いです。前途ある若者をバックアップしてやるのが大人の務め・・・だなんて心の底から思っている人なんているのだろうか。「若者には無限の可能性がある」とか「若者には夢がある」とか取りあえず言っておかないと若者ウケしないから、世のオッサンどもは朝礼や会議やミーティングで、さかんに若者を持ち上げてみせる。
しかし、一転居酒屋の掘りごたつに足を下ろせば、逆の論調に変化するわけである。
「最近のクソガキは世の中ナメきっとんなー」
「腹が痛けりゃ病欠、頭痛がしたら病欠、心がしくしく痛んだら病欠、どんだけ貧弱う〜」
「会社辞めるという連絡を親にさせる。子離れできない親もホイホイ子供の言うこと聞く」
「研修してもらって当然という顔。課題を出せば泣きが入る。誤認逮捕で留置所に入れられたような絶望的な表情をしやがる」
こんなしごく真っ当な本音を隠して、職場では若者に理解のあるオッサンを演じる・・・涙ぐましい努力に頭が下がる。
ぼくの部下は全員が若い。平均年齢24歳くらい。今スタッフは50人チョイいる。春には10人も入社してきたからまた増えた。ぼくはこいつらのことが嫌いだ。
「社員のことを嫌いなんて言っていいの?」との心温かなご心配は無用だ。「ぼくはなるべく嘘をつかない」「ぼくはたいていのことは内緒にできない」と部下に宣言してあるので、好きでもないものを好きというのは約束違反になる。嫌いなんだから、素直に嫌いと言ってよいのだ。
若者の何が嫌いか? そのすべてが嫌いだと言ってよい。
若いというだけの理由で、自分には何か特別な才がある、と根拠なく考えているゴウ慢さが嫌いだ。
仲間うちで「かわいー」「かわいー」と誉めあって、得意気になっている顔が嫌いだ。
何かというとケータイを取り出して、誰かにメールを送ろうとするのが嫌いだ。
お肉とジャンクフードばっかり食っているから、おならが臭いのが嫌だ。
肩からブラヒモ、背中からパンツを見せて、エロカワとか言ってはしゃいでる女どもが嫌いだ。
ふだんおとなしいのに、酒を飲んだら急に勇ましくなって職場改善とか言いだすヤツが嫌いだ。
親に生活費を見てもらっているのに、自立しているかのごとき言動をするのが嫌いだ。
恋愛をつかさどる脳みそがモンスター級に肥大しているのが嫌だ。
高価な革のコートやブーツをはいて、地球環境とかの心配をしてるのが嫌いだ。
自らの労働に、法定最低賃金以上の価値があると信じているのが嫌だ。
たいして可愛くもないのに、自分はそれなりのポジションにいると信じているのが嫌いだ。
「お金がない」といつも言っている割に、自分の食いたい物や着たい服にはバンバン金をかけるのが嫌いだ。
なにかちょっとある度にブログやミクシィに書き込むのが嫌いだ。
誰にも怒られたことがない、誰にもビンタを張られたことがない、ぬくぬくした生い立ちが嫌いだ。
春という季節が嫌いだ。春には大学を卒業したてのトンデモナイ野郎どもがやってくるからだ。。
今どきの22歳は、苦労の「く」の字も知らないのが大半を占める。採用面接で「今までで一番苦労した話してみて」とリクエストすると、「大学祭の準備で徹夜が続いたけど、それを克服して、無事お好み焼き店を出せた」みたいな話ばかりだ。
あるいは「サークルで仲間の意見が合わなかったんだけど、何度も話し合って無事ひとつになれた」みたいな。ほれって苦労話でなくて、楽しく退屈な青春ストーリーだろ。
自己紹介なんて聞いてしまった日には、金太郎飴がメビウスの輪と化したくらいの無限連鎖が続くのである。
「私は他人とコミュニケーションをとるのが得意です」
「私はたくさんの人と出会いたいです。そして出会った人とのキズナを大切にします」
「今まで築いてきた大切な人とのネットワークを・・・」
コラーッ!10人中10人が同じこと言うなーっ! オメエら、面接会場に来る前にガストかどこかで打ち合わせしてきたんかーっ?とぼくは暴発寸前に至る。
なぜ全員が同じ言葉を発するのか。その理由がわからない。一番売れてる面接マニュアル本にそう書いてあるのか。学校の進路指導説明会で就活担当の先生がそう言えとアドバイスするのか。それとも流行りの商業的ミュージシャンが語る愛だキズナだ出会いだ、というセリフを真に受けているのか。全国の大学が「コミュニケーション学科」みたいな謎めいた学科をポコポコ造り出したからか。そーいや、異文化コミュニケーションで名を馳せた語学学校は破綻したか。
とにもかくにも他人様との過度なコミュニケーションを信奉する全体主義者の党員たちが、どこか知らぬ草むらの奧の工場で大量生産されているような不気味さが背筋に走る。どんな社会でも、それがたとえ理想郷だとしても、意見の一致を見すぎている人間集団は不気味であり危険だ。
当社には、二十一世紀型の暴君が次々と現れる。入社1週間目にしてこんなリクエストをしてきたヤツがいる。
「私は他人に叱られて伸びるタイプではなく、誉められると伸びるんですね。昔から○○ちゃんは、誉められたらすごく頑張るよねって皆言ってくれるんです。だから私のいい部分を誉めていただけませんか」と言う。
そくざに右斜め45度から延髄切りをくらわしてやりたくなるのをグッと堪える。おまえは、小出監督のランニングスクール・小出道場にでも入部して「天才だね」と誉められ続けるがよい!
ちょっと希望職種を聞いてしまったがために、とんでもない要望を引き出してしまった事もある。
「そうですね〜、私は事業を統括する仕事をしたいと思います。私は他人に命令されるとやる気がなくなりますし、目的もなく何年も下積みをこなすのはムリです。学生時代のアルバイト先でも、○○さんは人の上に立つと能力を発揮するタイプだねって主任に言われましたし」
チクショウめ、鼻の穴から指つっこんで目の玉ポンッて出してやろうか!と全身をワナワナ震わせながら耐える。おまえは、アントンハイセル事業でも統括して世界の食糧危機を救うがよい!
先日は、入社1年目の女性社員が暇そうに横綱あられを食べていたので質問してみた。「来週採用試験があるので聞いておきたいんだけど、今どきの新卒学生はどうして皆同じ志望動機を言うの? 君はなぜウチの会社を選んだんだっけ?」。すると、彼女は横綱あられをバリボリしながら明るく述べる。
「今どきの学生さんには本音で語る志望動機なんてないんですよ。私がこの会社に就職したんだって、いつまでもキレいでいたいからって理由ですから。ほら、人前に出ている女性は何歳になっても美しさを保てるって言うじゃないですか。ここの会社は取材とかで人前に出る機会が多いだろうなって想像したんですよね」
おもしろいギャクを言うなあと感心し顔を見つめたら、どうやら真剣そのものである。クソーッ、お前のそのブ厚いファンデ顔を、大谷晋二郎ばりの顔面ウォッシュ攻撃で拭き取ってやろうか!
あるいは、企画会議に出席して何のアイデアも出さず、居眠り寸前の新入社員が堂々と見解を述べる。
「こういう会議の場では、もっと意見を言いやすいような雰囲気を作ってほしいんですよね〜。もっと楽しいムード作りをしたら、みんな自由にアイデアを言い合えて、会議が活性化すると思うんですよぉ」
わかった、今後わが社の会議は、死霊やハゲタカが群れ飛ぶ秘密結社の地下アジトの粛正会議のような雰囲気のなかで行ってやる。
こんな欲望むきだしの野獣的な連中を、まっとうな社会人に改造するのは至難のわざではないだろうか。何の共通項もないアカの他人が、ある日集まって突然運命共同体になる、それが企業である。特定の思考回路をもって集まる団体・・・宗教法人や政党やNPOやボランティア組織に比べ、営利企業とはほんとマカ不思議な人間集団なのだ。有名企業で給料がいいならその場に集まる理由はわかる。生活の安定であり、企業の看板が自らのアイデンティティの一部となる。しかし我々はその対極みたいなとこにいるしなぁ・・・。そんな不思議ユニットに起こる現象や問題を解決できる処方箋はどこにもない。そして、彼ら以上にバカまる出しで生きてきてしまったぼくは対処のすべを知らない。ただ祈り、ただ怒る。
さて、こんな連中も夏が過ぎ、落ち葉が道を濡らす頃には、それなりに苦労もし、たどたどしくも社会人敬語を使いはじめ、根回しを知り、そして知らぬ間にぼくよりも全然立派な社会人になっているのである。人間ってやつは、本当にすごいなと思う。
 特集1
特集1 特集1
特集1
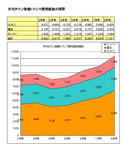


 ☆徳島うどん巡礼八十八ヵ所の旅☆
☆徳島うどん巡礼八十八ヵ所の旅☆ とくしまの生活情報紙さらら8月21日号の特集は、「突然の出来事に打ち勝て! 徳島人はこんなときどーする?」。ちょっと困った場面で、どんな行動をとるかを知れば、その人が見えてくる。たとえば…「『先日はお世話になりました』と言われたけれど、相手が誰だか分からなかったら?」「UFOを見てしまったら?」「家族でテレビをみているときに濃厚なラブシーンが始まってしまったら?」など、不意の出来事に徳島の人がどう対処しているかをアンケート! 県民性がみえてくるかも!?
とくしまの生活情報紙さらら8月21日号の特集は、「突然の出来事に打ち勝て! 徳島人はこんなときどーする?」。ちょっと困った場面で、どんな行動をとるかを知れば、その人が見えてくる。たとえば…「『先日はお世話になりました』と言われたけれど、相手が誰だか分からなかったら?」「UFOを見てしまったら?」「家族でテレビをみているときに濃厚なラブシーンが始まってしまったら?」など、不意の出来事に徳島の人がどう対処しているかをアンケート! 県民性がみえてくるかも!?  今回の特集は「わが店、渾身の一皿」。フレンチ、イタリアン、和食に中華…。さまざまなお店の26の一皿と26の料理人を紹介。ジャンルは違えど、料理に対する真剣な思いはみな同じ。店主の、この一皿を作りあげるまでの苦労や、一皿に込めるあつい魂。出来上がるまでの苦労があるからこそ、この究極の一皿が出来上がるんですね〜。そんな隠されたストーリーを知れば、格別の味わいになること間違いなし!さぁ、CU9月号でお店の最高傑作をさがしましょ〜!
今回の特集は「わが店、渾身の一皿」。フレンチ、イタリアン、和食に中華…。さまざまなお店の26の一皿と26の料理人を紹介。ジャンルは違えど、料理に対する真剣な思いはみな同じ。店主の、この一皿を作りあげるまでの苦労や、一皿に込めるあつい魂。出来上がるまでの苦労があるからこそ、この究極の一皿が出来上がるんですね〜。そんな隠されたストーリーを知れば、格別の味わいになること間違いなし!さぁ、CU9月号でお店の最高傑作をさがしましょ〜!





 徳島で大好きな彼との結婚準備を
徳島で大好きな彼との結婚準備を ☆徳島最強あそびまくり特集☆
☆徳島最強あそびまくり特集☆ 特集 ☆女ゴコロときめき料理ベストテン☆
特集 ☆女ゴコロときめき料理ベストテン☆



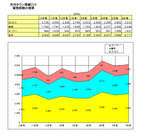
 ☆徳島の夏まるあそび大計画☆
☆徳島の夏まるあそび大計画☆